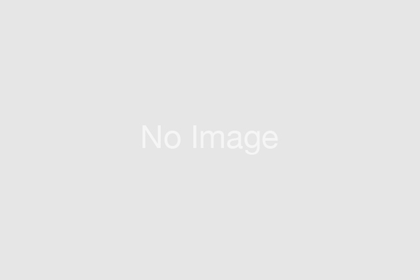大晦日から降り続いた雪にすっぽり覆われてしまった青森。
元旦は吹雪の中、雪かきからのスタートとなりました。
地震ではなく、世界では新たな戦争が始まってしまったのか。。。
雪に覆われても、静かな新年を迎えられたことにまずは感謝しなければと思う年明けです。
ーーー
さて本日よりフクシアンドフクシも新年スタートいたしました!
相変わらずの牛歩ではありますが、今年は午年にあやかって少しでもペースアップができればと思っております。
昨年もおかげさまでいくつかのプロジェクトに取り組み進めて参りました。
今年はそのうちいくつか工事がスタートいたします。
昨年は以前に蒔いた種がいくつか芽を出し、いよいよ花が咲く、そんな感じでしょうか?
ひとつひとつ大切に育てていきたいと思います。
本年もよろしくお願いいたします!

先日8日深夜に青森県東方沖で発生した地震は、同県八戸市で最大震度6強を観測しました。
幸い死者などは出なかったものの建物の被害は多く、被害に遭われた方々は大変な年末を迎えていらっしゃると思います。
1日も早く日常が戻ってくることを願っております。
ーーー
昨年大雪に見舞われたのとはうって変わって、今年はほとんど積雪のない師走となりました。
それでも仕事納めに合わせたかのように今季初といってもいいかのように降り積もり、市内はあっという間に銀世界へ。
遠く春を待ち侘びる本格的な冬の到来を実感しました。
ーーー
今年も多くの人に出会い、多くの機会に恵まれた1年となりました。
建築人として社会に出てから来年で30年。
青森に拠点を移してから26年になりました。
右も左も分からなかった頃、多くの諸先輩に教えられながらつくった建物も歳を取り、改修の話も多くいただくようになりました。
長い間、大切に使っていただいた建物に再会するたびに、建築をつくっていくことの責任と誇りを実感した1年でした。
と同時に、新たに生まれる建築に対しても、いつか再会する遠い未来を思ってデザインすることの大切さと感謝の気持ちを持って線を引いていきたいと改めて思っています。
ーーー
先日は青森中央学院大学さんで制作された広報動画が『大学広報メディアアワード2025』動画コンテンツ部門「次世代高校生共感部門」で銀賞を受賞された、とのビッグニュース!
「等身大のその先へ」というタイトルの動画は、学園の卒業生でありアンバサダーでもある王林さんが学生時代についてインタビューを受けているものです。(詳しくコチラをご覧ください!)
インタビューの場所は+C(ぷらす しー)で行われており、大学生活への憧れと希望に満ちた高校生たちにむけた動画に参加できたみたいな気持ちになり、とても嬉しく思います。
建築は人とそこでの営みによって大きくその表情を変えます。
多くの人に使われ、長く愛される建物を、ひとつでも多くつくっていきたいと改めて思いました。
+C(ぷらす しー)
ーーー

先日「『このまちに暮らしたい!』をカタチにするプロジェクト」
本年の完結編はDIY体験と交流会でした!
空き家リノベを学生さんと一緒に試行錯誤したプロジェクトは、様々な化学反応を起こしてくれました。
「建築をつくる」ためには、多くの人が関わっています。
そもそも「使う人」が居ないと建築は生まれてこないのです。
主人を無くした建物はその後どうなっていくのか。。。
色々試行錯誤はしていたものの、中々突破口が見えなかったときに手を挙げてくれた学生の皆さん。
『自分ならどう使う?』『誰に使ってもらいたい?』『自分たちにできることって?』etc.etc.
それをすぐさま行動へ。
その結果、2部屋が白い壁に生まれ変わり、そして先日のDIY体験と交流会となりました。
告知する時間も無い中、雪もちらちら降り出す寒い日に集まってくれた方々は、彼らが起こした行動によってつながった方々でした。

いきなりのアポにも快くいろんなお話しをしてくださったご近所さん。
今回のプロジェクトを聞きつけて、空き家リノベに興味津々の行政マン。
交流会には残念ながら参加できなかったけれど、差し入れをしてくれたお隣さん。
学生さんが壁を塗る、と聞きつけてレクチャーしてくれた塗装屋さん。etc.etc.
これまで出会うことがなかった人たちが出会って、建物は息を吹き返しました。
本格的に「使える」ようにするにはまだまだハードルは残っています。
けれど続けることで、さらに多くの人をつなげ「使われる」空間になっていくことを確信する機会となりました。
本プロジェクトに関わってくださった学生の皆さん、そして関係者の方々にこの場をお借りしまして改めてお礼申し上げます。
ありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いいたします!
ーーー
リノベーションは単なる物を新調することではなく、人の行き来を再度生み出すことなのかもしれません。
「Aomori Startup Center」「曲屋KANEKO」「みろく館」etc.etc. これまでも、こんな素敵な出会いがありました。
新年も様々なプロジェクトが続いていきます。
これからもきっと新たな出会いがあるに違いありません。
皆様にとっても良き出会いがありますように。
本年も大変お世話になりました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。


いつくるか、いつくるかと構えていましたが、とうとう冬将軍がやってました!
昨年も12月に大雪が降ったので、それに比べるとまだ優しい将軍なのでしょうか。。。
それでも日中も氷点下のような気温になると、顔も体もこわばってしまう青森です。
ーーー
先日のブログでもお伝えした空き家のリノベーション。
学生たちと一緒に壁塗りを行い、真新しい白いお座敷が現れました!
作業途中にご近所さんも覗きにきて、りんごと飲み物を差入れをいただいたり、じわじわ人の輪が広がってきているのを実感します。

さらにさらに、学生さんからのご提案で「綺麗になったこの場所を使って何かをやってみたい!」とのこと。
11月いっぱいの活動の予定は来週まで延長し、「空き家のDIY体験&交流会」を来たる12月9日(火)に開催することとなりました!
参加ご希望の方は弊社HPお問い合わせからもお申込みいただけます!

ーーー
手探りで始めた学生さんたちとの協同プロジェクト。
解体か継続か?
継続ならどんなカタチで???
継続するにはクリアしなければならないいくつものハードル。
とりあえずできるところから始めてみて見えてきたものはなんだろう?
9日はそんな話をしながら、次にできることを考えたいと思います。
小さな一歩だとしても、進み続けられたらどこかに辿り着く。
次の一歩を、学生さんたちと一緒にお茶でも飲みながらおしゃべりしにきてみませんか?


長い夏が終わったと思ったら、秋を越えていきなり冬がやって来たかのような寒さ。。。
でも、まだ昨年末のような大雪は八甲田山の山頂のみで留まっている青森です。
気温も暖かかったり寒かったり、で秋も戸惑っているかのよう。
紅葉した木々がいつもより鮮やかに見える気がします。
ーーー
さて、「空き家問題」は青森に限らず全国どこでも話題に上がっています。
私たちのすぐそばでもたくさんの空き家が控えています。
その一つ、青森駅に程近い場所にある小さな店舗付き住宅の空き家。
築50年超のこの建物は簡単には売却できない強者
解体にし更地にして土地を売却するには小さすぎて、解体しても初期投資は回収が難しい。
用途地域も防火地域に入っているため、新築のハードルが高い。
再利用するにはあちこち直さないと難しい。etc.etc.
増えすぎる空き家をどう活用していくのか?????
まさにリアルに向き合っていくべき建物に、わたしたちも試行錯誤してきました。
そんなとき「AOMORI未来創造ラボ」に手を挙げてくれたのが青森大学の学生さんたち!

ーーー
わたしたちは「『このまちに暮らしたい!』をカタチにするプロジェクト!」という空き家のリノベーションを一緒に考えてもらいたいと参加しました。
そして5人の学生さんが参加!
9月から実際に空き家を掃除したり、他の地域の先進事例を勉強したり、地域の方に話を聞いたり。etc.etc.
どんな使い方ができるのかアイディアを出しあったりしてきました。




たくさんのアイディアをまとめて発表!でも充分だったハズなのですが、学生さんからは「何かやってみたい!」とのラブコール(笑)
「今やれることって何だろう?」
そうして考えてみると意外にもたくさんあるのかな、と。
塗ってみる、掘ってみる、描いてみる、つくってみる、、、
建物を全体をフルリノベするのは確かに難しい。
スキル的に(大工さんをはじめプロの方には敵いません)
時間的に(今回のプロジェクトは11月いっぱいの期限付き)
お金的に(建物を蘇らせるにはかかります(涙))
法的に(建築基準法以外にも遵守すべきハードルがたくさんあります。)
決して簡単なことではありません。
でも!できることってあるよね!
で、行き着いたのが「壁を塗る!」です。
ーーー

11月末まで残り2回を6畳二間のお座敷の土壁(おそらく聚楽塗)を塗り替えることに決定!
先日、その1回目として養生(他の場所を保護するため)して、下塗りの作業を行いました。
学生さんにとっては、きっと人生初の壁塗り体験!
慣れない作業にいつしかみなさん黙々と。。。

来週はいよいよ本塗りです!
壁の色が変わるように、手探りだけど確実に何か変わっていく。
このまちを知らなかった学生さんたちも居場所ができることで何かが変わっていく。
私たち建築を空間を提供する人間として、そこに関わっていくことのリアルを改めて感じています。
ーーー
先日の作業を終えた頃には辺りはすっかり真っ暗。
ふと気がつくと、外の看板に点いているではありませんか!
店の内部と看板の照明が一緒に点く配線になっていたのです。
ということは、作業している明るいウチからお店は「営業中」になっていた!!!
閉まっていた空き家に明かりが灯る。。。
それだけでも通りが、まちが少し違って見えました。

ーーー
できることはまだまだあるみたい!
壁塗りに興味があるあなた、来週18日の午後、空き家を覗きにきませんか?
壁を塗るところから、一緒にやってみましょう!
(詳しくはお電話(tel.017-734-6225)または問い合わせフォームよりご連絡ください!)

暮らしのマルシェが過ぎ去り、山では雪が降ったとの便りも届いた青森です。
近所の木々も急いで秋一色。
冷たい雨が連れてきたのでしょうか?
気温もグッと下がって一挙に暖房の季節突入です。
ーーー

先日4日間に渡って行われました「暮らしのマルシェ」いかがだったでしょうか?
時折パラっと降ったりした曇り空の寒い日もありましたが、大きく崩れることはなくお天気にも恵まれた4日間となりました。
市役所から埠頭まで約1.4キロメートルの長いエリアを繋いだ今回のマルシェ。
何もかもが初の試みでしたので、実行委員は連日走りまくり。
200以上の出展者の皆さんのご協力により、何とか終えることができました。
ありがとうございました!
そして、きっと想像以上の長い距離にも関わらず、多くの方々に巡っていただきました。
足をお運びいただいた皆さん、ありがとうございました!


学生たちと試行錯誤しながらつくった屋台も何とか間に合い、勢揃い。
飲食はもちろん、農産物、クラフト、アートなど販売、体験、ステージ発表etc.etc.
本当に多種多様な方々の集合体に、来場者も老若男女みんなが楽しめるマルシェとなりました。


盛りだくさん過ぎて完璧な仕立てではなかったかもしれません。
ただ、会場でたくさんの方の笑顔に出会えたことは事実です。
出店者も来場者も関係なく「わぁーお久しぶりー!」の声を何回も聞きました。
多種多様なだけに、目的以外の商品との出会いもあったでしょう。
青森の素敵な暮らしが人々を繋いでいく姿を実感できる機会になったのではないでしょうか?

ボランティアの学生が言ってくれました。。。
「出展者も来場者も、実行委員もみなさん笑顔なのがすごい素敵だと思いました!」
疲労感は半端ない最終日でしたが、この言葉で救われた気がしました。。。
ーーー
これからも、引き続き手探りの「暮らしのマルシェ」が続きます。
今回参加していただいた出店者、来場者のみなさんの声を活かしながら。
そして一過性のイベントではなく、青森に根付いていくマルシェをつくっていきたいと思います。
一緒につくっていきたいと思うあなた!
実行委員として、出店者として、来場者として、どんなカタチでも大丈夫です。
暮らしを楽しむように、マルシェも楽しんでみませんか?
みなさん、来年、またお会いしましょう!


お盆が過ぎてもなかなか暑さは引かず、秋が待ち遠しく思っているうちに早くも神奈月に突入してしまいました。
日本全国、長ーい夏がやっと終わりを迎え、やっと夜長を楽しめるような季節になりました。
それでも桂の木は秋模様、甘い匂いが通りに薫る青森です。

ーーー
さて今度の週末、青森市の中心部ではとっても楽しみな試みが。
「暮らしのマルシェ」と銘打って、みなとまち青森のまんなか、全長1.4kmのストリートを舞台にマルシェが開催されます!
りんご箱一つから参加できる多様性にみちたマルシェで、さまざまな物産、サービス、パフォーマンスが行き交います。
「暮らすように営む」をコンセプトに、みんなで育む新しい形のマルシェです!
ーーー
私たちもオリジナル屋台の製作サポートなど春からさまざまなメンバーと共創してきました。
特に屋台のデザインは、八戸工業大学福士研の学生たちと一緒に考え、つくってきました。
学生たちにはモックアップも製作してもらい、考えたことが実現することの面白さも体験できたのではないかと思います。

ーーー
「一つの箱が展開して屋台に変身!」する屋台を目指して試行錯誤を繰り返し、先日やっと完成!
試運転(!?)を兼ねて街に繰り出しました。

市役所からフェリー埠頭までの1.4kmの長ーい道のりを、トコトコ、コロコロ、小さな箱はどこまでも行けそうです!
途中新聞社の取材も受け、開催まで少し、あとは天気が良いことを祈るばかり。。。
ーーー
マルシェの延べ出店申し込みは、4日間でなんと延べ550を超える見込み!
私たちもワクワク楽しみデス!
多様な出店者一覧はコチラから↓↓↓
https://kurashi-marche.com/vendor-list
マルシェを楽しみに来てくださる人はもちろん、参加者も楽しんでもらえるよう、ラストスパート!!!!
皆様、週末はぜひ「暮らしのマルシェ」へ足をお運びください。
オリジナル屋台が、ストリートのどこかで皆様をお待ちしています!

どこが梅雨だったのか思い出せない程、この1ヶ月は既に真夏日が続き、そのまま梅雨が明けてしまった青森です。
青森に限らず、熱中症に注意のニュースが飛び交う日本列島。
夏祭りの季節はますます長期間になって、青森もクーラー無しでは生活できなくなった。。。
温暖化は活実に進んでいる。そう実感している文月です。
ーーー
4月から弊社では八戸工業大学建築・土木工学コースの建築設計Ⅳをサポートしてきましたが、来週はいよいよ集大成のグルーブ発表会!
大学のサテライトキャンパスばんらぼにて25日(金)14時よりスタートします。
(ばんらぼはコチラ→→→〒031-0031 青森県八戸市番町9−5)
4月から製図、CAD、読み解き、住宅設計+発表、と結構ハードなスケジュールをこなしてきた学生達。
設計事務所の実践に近いお題にも試行錯誤、悪戦苦闘しながら取り組んできました。
最後はグループでの集合住宅設計。
設計すること自体、結構骨が折れることですが、他人と協同することは簡単なことではありません。
自分の考えを伝え、相手の考えを理解し、そこから一つのものをつくっていく。。。
色々手探りしながら、ギリギリまで作業を続け、なんとか提出にたどり着きました。
そしていよいよ、来週は八戸の街中で発表会!
製作と発表はまた別な緊張感が伴います。
今回もオープンな環境で行い、街ゆく人の目にも止まるかも⁉︎
ーーー
来年の今頃は、彼らの多くが社会人として歩み始めていと思います。
建築関係の仕事に限らず「協働」の場へと飛び込んでいきます。
私たちも設計事務所として多くの人と共に試行錯誤、悪戦苦闘する日々。
もがき、苦しみながらも出来上がった建築を目にすると、何故か救われたような気持ちになります。
そんな気持ちを少しだけでも体感してくれたなら。。。
来週の発表会はゲストクリティークに建築家の渡部良平さん(株式会社WAA代表)をお迎えしての開催です!
学生の熱い発表と建築家の本気コメントに、みなさまどうぞ足をお運びください!

春が一気に駆け抜けて、新緑が鮮やかな季節となった青森です。
日によっては夏の気配すら感じるほどの暑い日も。
全国的にはもうすでに30度超の気温を観測する地点も続出。
今年も長く暑い季節がやってきそうです。
ーーー
先日仙台メディアテークにて行われた「第3回JIA東北建築大賞2024」の表彰式に出席してきました!

素晴らしい作品と共に並ぶことに改めて感動を覚えつつ、大賞の「大熊町立 学び舎ゆめの森」の設計者の講演を拝聴。
東日本大震災から14年余り。
傷を負ったというよりも全てを失くした大熊町に完成した学舎。
それは震災後の新築した建物ではあるが、震災以前から「教育」に対する熱い想いが町にはあった。
それが芽を出し、こうして花を咲かせた。
そしてきっと、これからも多くの花を咲かせ続ける。
そんなことを想像し、ぜひいつか行ってみたいと思いながら、会場を後にしました。
ーーー
少し時間を巻き戻して。。。
表彰式が開催された仙台への道すがら、26年前に竣工した住宅へアフターのため久しぶりの訪問。
奇しくも「曲屋KANEKO」にも近い東北新幹線の七戸十和田駅で下車し、奥羽街道を北上したところにある住宅へ。
奥州街道は栃木県の宇都宮市から青森県の三厩(みんまや)までを繋ぐ日本最長の街道で、街道沿いには宿駅が百十四次もあったそうです。
東海道は五十三次ですから、その倍近くのある長い道のりを、車も新幹線も飛行機も無い時代、人々は歩いてもしくは馬に乗って移動していたのです。
この道を切り開いた先達の知恵や苦労はとうてい計り知れません。
「曲屋KANEKO」も築造から100年を超えて次の100年へと進んでいます。
100年前、大工たちもこの街道を材を運び、あの大きな建物を金物を使わずに組み上げ、地域の人々が協働して茅を葺いたのでしょう。
その茅が抜けて屋根が痛む毎に、皆で協働して葺くことを繰り返して今に至っています。
私たちが関わったのはその一瞬。
厩戸として使われなくなって朽ちかかっていた曲屋に、令和という時代を白い箱で埋め込みました。
こうして再び使われ出した建物は、街道のそばでこれからも行き交う人を見続けていくでしょう。
多くの人がこの曲屋屋根の茅を葺き替えてきたように、次の100年へ向けてつなぐデザインに関わることができ、本当に嬉しく思います。
クライアントと施工者、多くの関係者に改めて感謝して、私たちも道を進みます。
まだまだ細く先の見えない道ですが、進んだ先にきっとまた先達の足跡が見えてくる(ハズ)。。。
そんなことを思いながら街道を歩く晴天の一日となりました。
曲屋KANEKO 2020年 青森県七戸町

開花の知らせが届いたと思ったら一挙に満開へ。
桜の次には、りんごの花も咲き始めます。
若葉が芽吹き、淡い緑の空気に包まれる、そんな青森の春です。
ーーー
さてこの度「このめ〜Giving Tree AOMORI〜」が一般社団法人日本CM協会主催のCM選奨においてCM部門賞を受賞しました!
CMとは「コンストラクション・マネジメント」の略で、建設プロジェクトを進めるにあたり、発注方式の検討、設計者や施工者の選定、スケジュール・コストの管理などのマネジメントを行うことを指します。
私たちは大学で建築計画を学び、設計に入る前の段階の大切さを大小様々なプロジェクトで感じてきました。
小さな住宅を設計するときも、クライアントのたくさんの希望と様々な条件を集めて
それらを整理しなければ設計はできません。
公共施設や教育施設など、大きくなればよりたくさんの希望と条件が。。。
複雑で、毎回異なる諸条件を掬い上げ、整理すること、そこからデザインは始まっています。
今回単なるデザイン賞ではなくCMでの受賞は、そんなプレデザインを評価していただけたとのこと。
大変光栄に思います!
設計に入る前の(もしくは設計中も!)プレデザインにご理解をいただき、時間をかけてお付き合いいただいたクライアントの皆様に、改めて感謝申し上げます。
クライアントと私たち設計デザイン、施工者、その他様々な協力者がひとつのチームとなって、ともに建築をつくる。
そのチームを繋ぐことがCMの大きな役割なんだろうと感じています。
ーーー

「このめ〜Giving Tree AOMORI〜」は子どもたちの第三の居場所を目指し、商業ビルの2階の一角を改修したプロジェクトです。
大きな木の樹洞をイメージした青森ひばのルーバーに囲まれたひろばとその周りを囲む様々な居場所が子どもたちを迎えます。
青森にいても、県産材の青森ひばに触れることが少なくなっている現在。
もっと青森ひばに直接触れる空間がつくれないだろうか?と思っていました。
そこで「このめ」では、青森ひばのルーバーで空間を柔らかく区切ることに。
ルーバーは、貴重な原木を製材する際に端材として出てストックされているものを使用してコストを抑えつつ、青森ひばの大樹のような空間をつくることができました。
さらに、ひろばの床には青森ばの節アリの乱尺のもの採用し、塗装は子どもたちとの協働作業に。


小学校低学年の子どもたちも一緒にわいわい楽しみながら、気がつけばフロア全体が塗装完成!
無垢材本来の手触りや表情を残す植物油を浸透させる塗料で、子どもたちは直接青森ひばに触れ、香りを嗅ぐことができたと思います。
ーーー

階段には子どもたちのお姉さん代わりの高校生が大きな木を描いてくれました。
その枝葉が壁に、ガラス戸に伸びて、成長していきます。
まるで子どもたちのように。

完成からもうすぐ3年。
今日も大きな木に子どもたちが集まってきます。
ーーー
その場所だからこそ生まれる空間を探して、それを形にするために、丁寧なCMと設計デザインを私たちはこれからも続けていきます。
家を建てる、お店を開く、働く場所をつくるetc.etc.
そんなとき、どこからどう手をつけていいのか分からない方が多いようです。
まずは、お気軽に相談にいらっしゃいませんか?
きっとモヤモヤは少し晴れて、いろんなことが見えてくると思います。
お待ちしております!
このめ〜Giving Tree AOMORI〜 2022年 青森市

朝晩は薄手のコートだけではまだまだ不安ですが、
近くでは桜の開花の便りも聞かれ始め、やっと桜の開花前線が近づいてきたような青森です。
ーーー
新年度スタートして4月の前半が過ぎました。
アカデミックパートナーである八戸工業大学 建築・土木工学コース福士研究室でも、学生達が本格的にスタートしました。
本年度は2年ぶりに福士美奈子も非常勤講師として参加いたします。
2ヶ月前には初の街中での発表会を終えた先輩に引き続き、新たなシコウアンドサクゴがスタートです。

そのひとつとして、先日は築50年の空き家を調査!
スケール感を学びながら、これからも増え続けるであろう「マチノタカラ」をどう活用していくか。。。
ともに考えていきたいと思います。
これから約1年、どんな実を結ぶか、私たちも楽しみな春です。
ーーー
さて、来週22日(火)に一般社団法人日本建築まちづくり適正支援機構主催の「第8回 JCAABEリレートーク」に福士美奈子が登場いたします。
気がつけば、青森で設計を始めて27年。
事務所を構えて20年になりました。
様々な形でまちとつながりながら、次の時代へとどう繋いでいくか、日々の試行錯誤をご紹介したいと思います。
2025年4月22日(火)19:00~20:00
オンラインでの開催です。
以下よりお入りください。
ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/84345290527?pwd=iJCKOgagbugn9VmCSQOPUWZrDIvaib.1
ミーティング ID: 843 4529 0527
パスコード: 501470
後半はトークセッションとなっています。
ぜひお気軽にご参加ください。お待ちしております!


いよいよ新年度スタート!と気持ちが上向きになってくるこの時期。
先日、あたり一面真っ白に覆われた素森です。。。
冬に逆戻りか!?と一瞬思いましたが、その日のうちに太陽に照らされて綺麗に消えていきました。
ーーー

ウチに限らず多くの人がいろんな意味で動くこの季節。
春休み中には大学生がインターンシップで設計事務所の仕事を体験。
模型をつくり、オンラインでミーティング、PCでイラストへの着色etc.etc.
みっちり⁉︎スキルを詰め込んで新学期へ向かっていきました。

ひとつの建物をデザインするためには多くの作業と思考が大切です。
決まったルーティーンはありません。
手を動かしては、思考する。思考して、また手を動かす。
ある意味職人のような仕事かもしれません。
クライアントやプロジェクトが同じものは無いのですから、
デザインが同じものは無いのです。
タイパがよくない?コスパがよくない?
もの凄い速さで情報が飛び交う現代の中で、
思考錯誤しながら20年。
でもここは譲れない、ここがFFらしいところかなと思っています。
ーーー

そして今月からは新たなスタッフが加入!
以前インターンシップを体験して、このたび正式に一員に!
早速いろんなプロジェクトに巻き込まれます。。。
設計の実務(実状⁉︎)を体験しながら、しばらくは右往左往。
そしてたくさんの知識とスキルを得て、だんだんと試行錯誤。
30年くらい前は私たちもこうだったんだーと思いながら、
少し熱いミーティングが始まりました。
ーーー
物価高騰、各地での災害、読めない国際情勢、法改正etc.etc.
いろいろありますが、今だからこそ考える時!
フクシアンドフクシのシコウアンドサクゴにどうぞご期待ください!!

つい半月前には1m以上の積雪に覆われていたデッキもすっかり雪が消えた青森です。
三寒四温で気温の上下に振り回され、年度替りでそれもまた慌ただしいこの時期ですが、長い冬を抜けて春がやってくるワクワク感の方が勝る、そんな方も多いのではないでしょうか。
今年は特に津軽地方は大雪で、自然の脅威に何とか耐え抜いた感があります。
被害を受けた方も少なくありません。
日増しに強くなる日の光を浴びて一歩前に踏み出す、そんな今年の春はもうそこまで来ています!
ーーー
この度「曲屋KANEKO」が第3回JIA東北建築大賞にて建築賞を受賞しました!
日本建築家協会東北支部主催のこの賞は、2020年の第1回より隔年で開催されています。
これまで住宅で賞をいただいていましたが、一般建築部門での受賞は初めてです!
さらに、曲屋KANEKOは「グッドデザイン賞」「日本空間デザイン賞」「IFデザインデザインアワード」に続いて4つ目の受賞となりました!!
それぞれ評価されるポイントが異なる賞において、全国いいえ世界から多くの優れた作品が集まる中での4つの受賞はそうあることではありません。
この名誉はクライアントを始めとする多くの関係者のご協力あってこそです。
このようなプロジェクトに参加できたことを本当に嬉しく思います。
改めて、関係者の皆様、本当にありがとうございました!
そしてこれからも、お付き合いの程よろしくお願いいたします。

先日その三次審査で曲屋KANEKOを訪問。
当日はなごり雪というには本格的過ぎるお天気で、辺り一面雪景色に。
静かに降り続ける中、審査委員のみなさんをご案内しました。
大木の並木道と奥まで広がる牧草地のモノトーンの景色。
あと2ヶ月もすれば菜の花畑に変わるでしょう。
そして若葉が芽吹き、濃い緑に変わる頃にはジェラートのお店に長蛇の列。
牧草地を渡ってくる風を感じながら青空の下でゆっくりとした時間を過ごす。
曲屋だけでなくこの牧場全体にゆったり時間とした時間が流れているのは、やはり現地に来てみないとわからないものです。
そんな空気感を生む建築をつくりたい、改めてそう思いました。

100年そこにあり続けた曲屋は、白い箱を内包する「曲屋KAHEKO」として生まれ変わって次の100年へと向かっています。
今も試行錯誤しながらそこにあり続けています。
建築はつくって終わりではありません。むしろそこからがスタートです。
その建築が健やかにあり続けるためのデザインを私たちはしていきたい。
一人でも多くのひとに愛され、少しでも長く使ってもらえる建築を。
完成から早5年。
次の100年に到達するにはまだまだ遠い道のりですが、それでも着実に日々を重ねる曲屋に励まされた弥生となりました。
皆さんも、季節折々の表情で出迎えてくれる曲屋KANEKOへどうぞお足をお運びください!
曲屋KANEKO 2020年 青森県七戸町

来たる2月1日(土)、この度、八戸工業大学 建築・土木工学コース 福士譲研究室では、初の「街ン中卒業研究発表会」を開催いたします!
街中で、かつ、一般開放での発表というスタイルは、今回初めての開催となります。
当日は発表後に日本建築家協会会員による講評もあり、学生にとって新たな経験となればと思っています。
どなたでも入場可能です!ご予約不要。ぜひ足をお運びください。
日時:2025年2月1日(土)14:30開場(発表・講評15:00)〜17:30
会場:八戸工業大学 番町サテライトキャンパス「ばんらぼ」(八戸市番町9-5協栄八戸番町ビル1階)
お待ちしております!

2025 年が幕を開けました!
皆様、今年もよろしくお願いいたします。
昨年末から怒涛の如く降り続いた雪、雪、雪。
青森の雪景色が全国区のニュースに度々登場する、そんな幕開けとなりました。
昨年の冬は記録的に積雪が少なかったため、余計に堪える久しぶりの大雪(涙)
寝正月ではいられず、ひたすら雪かきの毎日となりました。

ーーー
さて今年のF+F、雪に埋もれながらも何とか始動いたしました。
年頭にあたり振り返れば、昨年はチャレンジの多い一年でありました。
・八戸工業大学でのプロフェッサーアーキテクトとしての本格始動。。。
・まちと共存する建築の実装。。。
(まちのオアシスの完成、青森市新市庁舎の景観賞受賞、正門ひろば eⁿの日本空間デザイン賞受賞)
・そしてもちろん、設計デザインもetc.etc.
(風のホリゾント、本棚の家)
ーーー
今年もチャレンジは様々続いていきます。
そして2025年、F+Fは設立20周年を迎えます!
もう20年という気持ちと共に、まだまだ道半ばという思いも。。。
これまで支えてくださったクライアントを始めとする関係者の皆様に感謝申し上げるとともに、これからの20年、さらにはその先を描きながら一歩ずつ進んでいきたいと思います。
ーーー
そこで、2025年の今年は「創」という字を掲げて動きます。
建築を、空間を創るのはもちろん、想像し、想像する。。。
昨年までチャレンジし、考え続けたことをカタチにしたいと思っています。
ーーー
世界は今、様々なことがザワザワしています。
青森でもこの雪は災害級です。
それでも青森の人々は生きています。
毎日雪をかき、車も人も動きづらい毎日を生きています。
時折見せる青空と太陽に、来る春を思って生きています。
大変な冬も、明るく楽しく生きていく努力をしています。
これは凄いことではありませんか?
ーーー
私たちは考えます。
こんな大変な時も人々に安らぎを与える建築は?
人々が抱える難題を解決する建築は?
困っているまちや人々を勇気づける建築は?
そんな建築は一朝一夕でデザインできるものではない、と20年作り続けてきて痛感しています。
だからこそこれからも考え続け、創り続けたいと思います。
小さな小さな一歩ですが、前に進んでいることを信じて。
年頭にあたり、20周年にあたり、夢を掲げて初心に帰ることの大切さを改めて感じています。
あたり一面、真っ白に雪に覆われる青森ならではの良いところを再発見した年明けとなりました。
本年もフクシアンドフクシをよろしくお願い致します。

いよいよ白いものが降り出し、遠くの山々も白い帽子を被り出した青森です。
明日から師走、2024年もあと1ヶ月となりました。
今日はいつもと違う体験の備忘録を少々。。。
ーーー
青森県林政課主催の「地域材活用ワークショップ」に参加。
地域材に関する「川上(かわかみ)から川下(かわしも)までを知ることから」ということで、雪がちらつく中伐採現場へ。
メインで伐採マシーンを操るのは20代(おそらく)の若者。
マシーンであっという間に数本を切り倒した後は、マシーンでは難しい大木にチェーンソーで切り倒しにかかる。
高さは25m超、樹齢は50年くらい、二股になったこんな特殊解はマシーンでは難しいらしい。
曇天の寒々しい山の中で、「カーン、カーン」と最後の打ち込みの後に、静かだけど大地に響く「ドーン」という音と共に大木は横倒しになった。
チェーンソーを木にあて始めてから10分もかからなかったように思う。
(その瞬間の動画はFBに。)
二股の大木は、短く残っていた木を避けるように倒れていた。
聞くと、この短い木はあらかじめ残しておいた転がり防止の木だという。
それを計算してチェーンソーの入れ方を調整して倒していくらしい。
言うのは簡単だけれど、現場で目の当たりにすると、あまりの精密さに驚きを超えて感動すら覚える。
青森の川上(かわかみ)にはすごい若者がいる。。。

ーーー
その後は川中の製材所へ。
ちょうど下北からやってきた巨木を製材していた。
製材所の建物は100歳になるとか。。。
さっき切られた木よりも長い間、青森の林業を支えてきた。
この場所を次の100年へ繋いでいくにはどうしたらいいのだろう。。。

ーーー
私たち川下(かわしも)の人間にできること、それを考える機会はここ数年特に増えています。
これまで住宅をデザインするときはほとんど木造でしたので、毎回木とは向き合ってきました。
毎回異なる空間に見合った「木」は何だろう、と。
そんな中で、もちろん県産材も多く使ってきました。
杉、青森ヒバ、唐松を、柱に土台に床に下地に家具に、etc.etc.
最近は住宅に限らず、中大規模建築の木造化がSDGsの観点からも広がってきています。
私たちがデザインした正門ひろばeⁿでは、ベンチへと生まれ変わらせることにしました。
大きくなり過ぎて手入れが難しく、学園が見えなくなってしまっていたヒマラヤスギを伐採するにあたり、別な形で残したいと考えたのです。
チェーンソーを巧みに操る現代版キコリが、幼稚園児の見守る中ヒマラヤスギを伐採。
乾燥され、製材され、座板にして、学園祭で焼印を押すイベントを開催しました。


それらを座面にしたオリジナルのベンチとなって、ヒマラヤスギは再び同じ場所に戻ってきました。
かつてあった大木はキャンパスでの思い出と共に多くの人の記憶に残ることになったのです。

ーーー
「川上(かわかみ)から川下(かわしも)まで」
ヒマラヤスギがベンチになるまで、多くの人々が関わりました。
このヒマラヤスギもたった6本とはいえ県産材。
青森の豊かな資源を未来へと繋ぐデザインを、これからも続けていきたいと思っています!
次回も私たちがこれまで関わってきた県産材をご紹介。
どうぞお楽しみに。

今年も残すところ2ヶ月を切りました。
桂の木もすっかり葉を落として甘い香りがする青森です。
ーーー

先週は今年度最後のインターンシップの学生さんが来社。
青森田中学園の「正門ひろば eⁿ」や「+C」を実際に見てもらう機会がありました。
そして完成したばかりの風除室も!(←こちらは近日改めてご紹介いたします!)

実際に打合せにも参加したりと、設計事務所の仕事の一端は体験できたのではないでしょうか?
そして事務所に戻って、設計というには程遠い資料集めから作業に入りました。。。

きっと頭の中は「?????」の状態だったはず。。。
でもそれは大切な時間で、私たちは設計(デザイン)の線を引くまでに多くの準備をします。
住宅の設計でしたら、クライアントとじっくり話をし、どんな家をつくりたいと考えているのか、その希望内容を伺い、予算のお話や敷地の条件などを詳しく調べます。
住宅以外も、店舗やオフィス、学校や美術館など様々なプロジェクトも同様です。
様々な情報を整理して、答えを探していきます。
そして設計、工事を経てやっと完成に至る。。。
そんな私たちの仕事をちょっとでも知ってもらえればと思います。
ーーー
「設計をやってみたい!」と思う諸君!
設計事務所の仕事を体験しに、学びにきてください。
わたしたちはいつでも大歓迎です!
(インターンシップ、オープンデスクのお申込みはお電話(017-734-6225)またはメールにて!)

朝晩の気温がぐっと下がり、店頭には新米とりんごが並び、一挙に秋がやってきた感満載です。
ここ数日はお天気も良く、紅葉の見頃を伝えるニュースに思わず遠くの山々を見る青森です。
ーーー
さてこの度、「正門ひろば eⁿ」が日本空間デザイン賞にてShotlist(入賞)を受賞しました!
国内外から800を超える作品が集まった中から、「10.公共施設・コミュニティー空間」カテゴリーにて、3年前の曲屋KANEKO(銀賞、サスティナブル賞)に続いての受賞です。

先日、東京での表彰式に出席してきました。
次々と多くの素晴らしい作品群が紹介され、さらに2024年の大賞も発表。
受賞の嬉しい気持ちとともに、これからも「いい建築」「いいデザイン」を目指そうと気持ちを新たにしました。

「いい建築」「いいデザイン」の答えはまだまだ手探り、毎回シコウサクゴを繰り返しています。
「正門ひろば eⁿ」でも青森田中学園のみなさんと一緒に考え、悩み、つくってきました。
その過程の先にしか答えは見つかりません。
これからもシコウサクゴを続け、答えを探していきたいと思います。
改めまして、関係者の皆様に感謝申し上げます。
この度は受賞、おめでとうございます。
そしてありがとうございました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

正門ひろば eⁿ 2023年 青森市

久しぶりのまとまった雨が降っていますが、気温はまだまだ高い青森です。
この度、青森市新市庁舎がGOOD DESIGN AWARD 2024を受賞いたしました!
ーーー
青森市新市庁舎は5社の設計共同体の一員として携わっており、第16回ふるさとあおもり景観賞最優秀賞に引き続きの受賞となりました!
評価コメントには、「シンプルだが強い都市軸は、日常的な使われ方をすることによって街の構造を常に意識させるものとなり、また防災や市庁舎の拡張性にも寄与する、考え抜かれた配置計画である。(抜粋)」とあり、プロポーザルの当初から描いていた青森の街全体を俯瞰する視点とその配置計画を評価していただけたようです。
多くの方々と共につくった南北を貫く広場とサードプレイスが、受賞をきっかけにますます使ってもらえることを願わずにはいられません。
そして、そのにぎわいが街全体へじわっと広がっていくような空間をこれからもつくっていきたいと思います!
GOOD DESIGN AWARD 2024の詳細はコチラをご覧ください!


2024年度前半も相変わらず走り続けた半年となりました。
足掛け3年のプロジェクトが完成し、いよいよ呼吸を始めます。
青森市中心部の国道4号に程近い場所に、葬祭業を営む会社の本社を新築するプロジェクト。
ここには本社機能だけではなく、遺体安置施設とエンバーミングセンターを併設しており、
こちらは先行して昨年完成、すでに稼働しています。
そして今年本社が完成、移転、そしていよいよ稼働を迎えます。
ーーー
 第1期工事の「いのりのいおり」各部屋では野坂徹夫氏作の天使のレリーフが優しく出迎える
第1期工事の「いのりのいおり」各部屋では野坂徹夫氏作の天使のレリーフが優しく出迎える
私たち誰もが避けて通れない「別れ」。
普段はそれから目を背けて生きている、と言っても過言ではありません。
でもそれは、誰にでも平等にいつでも隣り合わせであることに気が付くときがあります。
今回のプロジェクトは、それらとじっくりと向き合って考える時間を持つことができました。
大切な人を失ったご遺族と、それに寄り添うスタッフにとって、どんな場所があったらいいのか。。。
世界中には様々な死生観があることを一から学び、この場所にどんな空間をつくったらいいのか。。。
そしてこのまちにどうあるべきか。。。
ーーー
八甲田山へとつながる「観光通り」という名の道に面して、まずは明かりが灯ります。
敷地の3方に通り抜ける配置計画と、大小様々な箱が並ぶようなデザインで近隣の街並みを増幅させました。
スタッフと来客、そしてこの街に住む人々の新たな場所として息づいていきます。
詳細についてはこれから数回に分けてブログにてご紹介しながら、近日中にWorksにもアップいたします。
どうぞお楽しみに。。。

 表彰式には多くの方が。基調講演も二つの事例紹介も大変興味深かったです。
表彰式には多くの方が。基調講演も二つの事例紹介も大変興味深かったです。
もうすでに夏が来てしまったのか???
梅雨はどこへ???
と感じてしまうほど、夏日が続いている青森です。
ーーー
さてこの度、私たちが設計チームとして参加しました「青森市新庁舎」が青森県の景観賞を受賞しました!
先日行われた「令和6年度景観フォーラム」にて、西市長が宮下知事から賞状を受け取りました。
プロポーザルにて設計者として選定され、当初の10階建から一部アウガへ関係部署が移転することとなり3階建を再設計。
工事完成後、全世界でコロナ渦へ突入。
予想だにしないこの10年でした。
先には日本建築学会の新人賞にも選出され、建築雑誌「新建築」に掲載され、多くの客観的なご意見をいただけるようになりました。
住宅とは違い、多くの方々が利用する公共建築。
より多くのご意見、感想を受取ながら、次のデザインに活かしていきたいと思います。
関係者の皆様、そして利用している市民の皆様、ありがとうございました。
これからもよろしくお願いいたします。
 西市長が代表して宮下知事から賞状授与。設計時に西市長は市民WSに参加してくださっていました!
西市長が代表して宮下知事から賞状授与。設計時に西市長は市民WSに参加してくださっていました!
ーーー
そしてもう一つ嬉しい知らせが。
「正門ひろばen」が「日本空間デザイン賞2024」LongListに選出されました!
こちらも多くの方々が利用する公(おおやけ)の建築。
正門でありながら、地域に開かれた場所としてデザインしました。
元々、10年後の未来を見据えてキャンパスグランドデザインを描き、その第一歩が「正門ひろばen」です。
学園の建学の精神「愛あれ 知あれ 真実(まこと)あれ」を英語表記にしたモニュメントは、多くの学生の目に留まるようになりました。
卒業生の王林さんが出演する学園CMにも、ワンシーンが組み込まれています!(15秒の中の一瞬です↓↓↓)
その様子は、通りを行く車や人の目にも。
コンセプトは、「様々な人がふっと立ち止まるような「とまり木」のような場所」
学園の新しい顔として、これからもっともっと使われていくでしょう。
今後も進化し続ける学園を、建築の目で見続けていきたいと思います。
ーーー
住宅のような個人の建築も、周りがあってこそ。
小さいも、大きいも関係なく、常に周りを意識して、「どう開くか」「どうつながるか」デザインしてきました。
これからもそれは続きます。
そしてもうすぐ、また新たな公(おおやけ)の建築が完成します。
そちらはまた改めて。
どうぞお楽しみに。

お天気のいいままゴールデンウィークが過ぎ、次の夏休みまでしばし仕事モードに戻った青森です。
GW明け、今年度のインターンシップがスタートしました!
今週から学生さんが事務所に来てくれています。
期間は様々ですが、1〜2週間のケースが多いです。
もう少しで完成を迎える現場の見学、プランニング前のボリューム算定作業などなど。。。
計画から設計、工事監理までの様々な設計事務所の仕事をほんの少しでも実感してもらえますように。。。
ーーー
そしてまた1通のインターンシップ希望のメールが届きました。
なんとその学生さんは数年前の「お仕事体験イベントの参加者」だそう!
目をキラキラさせて参加してくれた子供達。
彼らがこうして建築の道に進んでいることを実感して、なんだか勝手に嬉しくなりました。
また少しずつでも、仕事体験の機会を作っていきたいと改めて思ったGWでした。
ーーー
さて!この度来週5月17日(金)に弘前のオランドさんで開催の「日替わり建築バーテンダーvol.12」に参上いたします。
カフェとギャラリーとゲストハウスを内包し、なんだか素敵な雰囲気を醸し出しているオランドさん。
ずっと行きたかったのに機会を逃していたので、とっても楽しみです。
「建築バーテンダー」のお役目を果たす、というよりは純粋にその空間に浸りに行く気満々です(笑)。
新年度1回目での機会に「女性建築家として、チームの主宰者として、母として、など様々な視点を持っている」なんて過大なご紹介をいただいていますが、これまでの亀の歩みを少しご紹介できればと思います。
よろしかったら足をお運びください!(福士美奈子)
 リビングの木サッシを開け放つとパノラマビューが広がります。
リビングの木サッシを開け放つとパノラマビューが広がります。
すっかり葉桜になって、今度はりんごの花が満開に近づいている青森です。
いきなりの夏日となった週末。
つがる市で開催したオープンハウスは無事終了いたしました。
ゴールデンウィークがスタートし、絶好の行楽日和にもかかわらず足を運んでくださった皆様、ありがとうございました。
ーーー
 落ち着いたアースカラーの天井と壁が、折り紙のような空間。
落ち着いたアースカラーの天井と壁が、折り紙のような空間。
先日もご紹介したように、この家の特徴はこの長い本棚。
たくさんの本が並び、これからの暮らしに寄り添って表情を変えていくことでしょう。

オープンハウス終了後にはクライアントご家族もご来場。
もう間も無く引渡しと引越し。
私たちも思い切り空間を味わう1日となりました!
 黄砂で霞む夕景。一気に芽吹いた緑がとても綺麗な一日でした!
黄砂で霞む夕景。一気に芽吹いた緑がとても綺麗な一日でした!
全貌は近日HPにて公開予定です。
どうぞお楽しみに!
 近くの桜もすでに満開です!
近くの桜もすでに満開です!
先週は、まだ桜の開花宣言前でしたが、今週末には満開を迎えた青森です。
桜の開花時期は短い印象はありますが、いつも以上にあっという間のような気がします。
年々短くなるようなこの季節ですが、だからこそワクワク感も凝縮されるのかもしれません。
ーーー
さて、来週のオープンハウスまであと1週間となりました。
現場では仕上げの最終段階を迎えています。
LDK、フリースペース、書斎などいくつもの空間を、ひと繋がりの天井がすぽっと覆う今回のデザイン。
落ち着いたカラーの内装が光を柔らかく拡散します。
 アースカラーの壁も仕上がりました。吹き抜け越しに入る光が柔らかい印象に。
アースカラーの壁も仕上がりました。吹き抜け越しに入る光が柔らかい印象に。
今回のデザインキーでもある長い本棚も、もう少しで完成。
単なる本棚ではなく、読書スペースや階段スペースを生み、そしてプランの空間を分節し、かつ繋ぎます。
 空間を貫く長い本棚。
空間を貫く長い本棚。
外回りも最終段階。
東西に長い敷地を使い、庇が直射日光を遮ります。
リビングのデッキ前には水盤も。
年々真夏日も多くなりつつある青森の夏を涼やかにしてくれます。
 紙を折ったようなフォルムで一連につながるボリューム。その下に伸びる薄い薄い庇。
紙を折ったようなフォルムで一連につながるボリューム。その下に伸びる薄い薄い庇。
勾配屋根を活用した2階は、階高も低く抑えてロフトのような雰囲気に。
1階の吹き抜けから緩やかにつながる空間と奥まで連なる本棚は圧巻です。
ぜひ、この機会をお見逃しなく。
ーーー
今も地域の暮らしを守り続ける「かっちょ」
この家の「かっちょ」も、クライアントご家族の暮らしをこれから守っていきます。
八重桜が満開になるであろう1週間後に、
本物の「かっちょ」探しながら、この場所ならではの「かっちょ」を見にドライブはいかがでしょうか?
ーーー
まだもう少し空きがあります!
見学ご希望の方は、お電話(017-734-6225)またはメール(ffarchi@w5.dion.ne.jp)までご一報ください。
その際にお名前、ご連絡先、見学ご希望時間をお伺いいたします。
その後、開催場所についてのご案内をお送りいたします。
お申し込みは4月25日(木)まで。
お待ちしております!
 庭先のさくらんぼの木も今まさに芽吹かんとしています
庭先のさくらんぼの木も今まさに芽吹かんとしています
つい先日まで朝晩の暖房が欠かせなかったのに、この週末は一転20度超の青森です。
あまりの雪の少なさに、春の到来は昨年以上に早くなると覚悟していました。
でもその予想を裏切って3月は中々暖かくならず、今週になってチラホラ桜の開花が聞こえてきました。
ただ、気温の上がり方は優しくなく、全てのつぼみが一挙に咲いて、あっという間に散ってしまうのではないかと感じます。
そして夏がすぐそこまで来ているような、年々短くなる春ですが、いつも以上に慌ただしい今年の春です。
ーーー
さて、昨年より工事が進んでおりました住宅がいよいよ完成いたします。
雪が少ないのは工事する側としては大変有り難いことで、新緑の季節にお引き渡しとなりました。
そのお引越し手前のタイミングで、クライアントご家族のご厚意によりオープンハウスの開催です!
場所はつがる市。。。
そう!先場所110年ぶりの快挙を成し遂げた尊富士が中学時代を過ごした場所です!
(尊富士さんの住宅ではありません、念の為。。。)
つがる市は青森県の中西部に位置し、南に岩木山を望み津軽平野が広がり、一部は日本海にも接しています。
青森程積雪量は多くはありませんが、広大な平野を吹き抜ける風がとても強く、冬の寒さは大変厳しい地域です。
でもその気候がもたらす美味な果物や農産物が豊富な地域でもあります。
そんな場所に今回の住宅は建っています。
ーーー
 塗装と外構の工事が進んでいます。
塗装と外構の工事が進んでいます。
北西よりの強い風を「かっちょ」のような壁で受け止めつつ、雨雪を片流れの屋根と一部南側開口部の軒先空間を生み出す下屋とで構成したデザイン。
「かっちょ」とは津軽弁で、地吹雪(じふぶき)体験ツアーがあるほどの強風が吹き荒れるこの地方特有の防雪柵(防風柵)のことです。
木製のものから鉄製まで様々で、家や道路を地吹雪から守ってくれます。
そんな「かっちょ」のような壁と屋根で守られて、内部には伸びやかなプランが広がっています。
その東西に長いプランに沿って伸びる長い本棚。
本棚が部屋を間仕切り、かつそれぞれの部屋を繋ぎます。
勾配屋根による空間を大小様々な梁と柱と長い本棚が、吹き抜けの空間に変化を与えるデザインです。
 勾配天井と斜めの梁、そして最後に本棚が組み込まれて完成へ!
勾配天井と斜めの梁、そして最後に本棚が組み込まれて完成へ!
ーーー
現在、工事は最終仕上げの段階。
私たちも我が子の旅立ちを見守るような、少し寂しい、でもワクワクするこの時期です。
写真では味わえない空間の実体験ができる貴重な機会です。
お出かけするには絶好の、4月27日(土)1日限りの開催です。
ぜひ、足をお運びください!
ーーー
見学ご希望の方は、お電話(017-734-6225)またはメール(ffarchi@w5.dion.ne.jp)までご一報ください。
その際にお名前、ご連絡先、見学ご希望時間をお伺いいたします。
その後、開催場所についてのご案内をお送りいたします。
お申し込みは4月25日(木)まで。
お申し込み多数の場合は先着順となりますので、ご了承ください。
お待ちしております!
 家を、家族を、町を見守ってきた大きな欅
家を、家族を、町を見守ってきた大きな欅
啓蟄も過ぎたのに今頃雪景色に戻った青森です。
でも今日は時折日が差し、ふわふわと雪が舞って地面についた途端消えていきます。
春がそこまで来ていると実感しています。
さて、先日アップした「BEARS」のデザインコンセプトについてご紹介です!
長い間「町のお店」としてあり続けてきた店舗をリノベーションしたプロジェクト。
その背景と経緯、そこから生まれたデザインについて少し詳しくご紹介いたします。
ーーー
場所性と空気感を読む
緑豊かで果物で有名な町のメインストリートの交差点の一角に立ち、店は町ずっと明かりを灯してきた。
代々食品や日用品を販売してきた店舗の改修。
店の奥に住まいがつながり、奥に行くに従って傾斜している場所だった。
登りきったところには立派な欅の大木があって、そこには気持ちの良い風が吹いていた。
車の往来が途切れた瞬間に聞こえてくるのは、小さなお手製の池に注ぐ井戸水の音だった。
その水面を揺らし続けるなんとも清らかな音は、店を営む家族と共にずっと一緒にあり続けてきた。
そんな穏やかで静かなところにこの建物は立っている。

時代の流れに沿って様々な商品やサービスを提供し続けてきたこの店は単なる店ではなく、「商店」という名の地域に開かれたサードプレイス的役割を担ってきた。
その明かりは絶やすことなく、これからもカタチ変え続いていく。
新しいモノを組み込みながら。
クライアントにとって子供時代を過ごしてきた我が家は、今は新たな家族と一緒に里帰りする場所であり、これからは職場の一つとなる。
インターネットの発達により、場所を問わず仕事ができるようになり、働き方も暮らし方も複数拠点を持つスタイルが珍しくなくなった昨今。
クライアントは慣れ親しんだこの場所をその一つとして選んだ。
今までの暮らしに新たな家族の時間がプラスされる。
多くのまちの人々が出入りしていたこれまでの役割を受け継ぎつつ、新しい家族が豊かな自然を感じながらのびのびできる器をデザインした。
ーーー
 新築祝の鏡に映る改装前の店舗。暖かいオレンジ店内の雰囲気は残して改修することに。
新築祝の鏡に映る改装前の店舗。暖かいオレンジ店内の雰囲気は残して改修することに。
オレンジの中に入れた白い箱
長年地域に親しまれてきた店の雰囲気は極力残し、既存壁と床の色は近似色のオレンジ系に。
3方に開かれた空間はそのままに、その中に新しい白い箱を埋め込んだ。
 3間×3間のワンルームにはミニキッチンと洗濯機、大きな書棚を。
3間×3間のワンルームにはミニキッチンと洗濯機、大きな書棚を。
3世代の家族が集まって炬燵を囲んでもちょうど良い広さ。
白い箱には大小様々な開口部を設け、三方どこからでも出入りできる。
パソコンを開いて仕事する傍らで、子供たちは内外関係なく遊び回る。
 箱の中には1本の既存の柱。炬燵を置いて読書とコーヒーを楽しむ。
箱の中には1本の既存の柱。炬燵を置いて読書とコーヒーを楽しむ。
盆地のような気候で夏の暑さも、冬の寒さも厳しいこの地域。
そんな季節はガラス戸を閉めてオレンジの空間をバッファーゾーンとし、少ないエネルギーで高効率の温熱環境を実現する。
地域産の杉の無垢の15mm厚の床は空気をはらみ、温度変化を緩やかにする。
夏は打ち水をし、冬は炬燵。。。
完璧にコントロールされた温熱環境ではなく、季節の移り変わりを感じて暮らしていく、ある意味豊かな環境がここにはある。
ーーー
つないでいくモノに新しいモノを足して生まれるデザイン
 まちに開かれた大きなガラスには、オレンジの店の中に白い箱が浮かび上がった。
まちに開かれた大きなガラスには、オレンジの店の中に白い箱が浮かび上がった。
時代の変化、家族の成長と共に建物は変化できる。
それぞれ多様な暮らしと働き方のカタチはどこから生まれてきたのか、それを読み解くことが大切だと思う。
そしてこれから、共に暮らし、働くクライアントご家族の新たなフェーズをどう入れ込むか。
この場所、この建物でしかできないデザインはそこから生まれてくる、と思っている。

昔からずっと続いているようなオレンジの空間が、今までと同じように常連さんを招き入れる。
クライアント家族が、ここを訪れるまちの人がオレンジと白を行き交う。
白い箱にはこれからきっと、たくさんの本や写真、絵が飾られて、いろんな色が重ねられていくだろう。
「つないでいくモノ」に「新しいモノ」を足して、「これから」が育っていく。
ーーー
人口減少、過疎化が問題視されている現在、どこにでもあるようなお話しでしょうか?
いいえどこにでもありそうで、唯一無二の家族や営みがそこにはあります。
ならばデザインも一つとなく同じものはありません。
そこにしかないデザインこれからも探し、描き、創り続けていきたいと思います。
BEARS 2023年 青森県

二月半ばを過ぎたばかりだというのに昨日は20度近い気温となった青森です。
年明け早々の甚大な被害をもたらした能登半島の震災。
被災者の方々に心よりお見舞い申し上げます。
1日も早い復興を願っております。
東日本大震災からもう少しで13年。
改めて平穏な毎日に感謝し、自分にできることをしっかりやらなくては、と思う今日この頃です。
ーーー
そんな中、背中を押してくれる嬉しいことも。
先日本屋の店先で目に止まった雑誌、北東北にフォーカスしてその魅力を伝えている「rakra(ラ・クラ)」
表紙の美味しそうな料理の写真に思わず手に取ると、何と!お二組のクライアントが登場しているではありませんか!!!
その姿に勝手に喜んで、設計時のことと、その建物を思い出して、力をもらいました。
他にも青森の、そして北東北の魅力的な記事と写真がたくさん!
ぜひ、お手にとってみてはいかがでしょうか?
ーーー
そして嬉しいことがもう一つ。
私たちが設計共同体の一員として手がけた「青森市新市庁舎」が新建築1月号に掲載されました!

プロポーザル開催が決まる前から「青森の新しい庁舎はどうあるべきか?」を「アオモリボイス」という公の場で多くの人と意見を交わしてきた時から何年経ったのでしょう。
10階建ての計画は、市長交代を経て窓口機能をアウガへ、防災機能を担う執務機関などが新市庁舎に整備することとなり、縮小して再設計となりました。
2019年9月に工事が完成し、運用開始したのが2020年1月。
今思えば、設計が始まる前から共有されていた「サードプレイス」の概念。
市民のための市役所とは?を考えたときの漠然とした思いがカタチとなった「サードプレイス」なのです。
従前の「多目的スペース」とは一線を画す「サードプレイス」。
社会学者レイ・オルデンバーグが執筆した”The Great Good Place”
その翻訳本には、「家でも職場でもない誰にとってもとびきり居心地のよい場所」というマイク・モラスキー氏のが訳ついています。
振り返るとこれまでもこのブログで「サードプレイス」について幾度となく書いてきました。
例えば、
多くの人と意見を出し合い模索したこの場所をどう使っていくか、いよいよだ、という時にコロナ禍を迎えました。
そしてそれが5類となった昨年、市庁舎の目の前では多くの人で賑わうねぶた祭りが開催されました。
「サードプレイス」が本格的に使われるかどうか、がやっとスタートしたと言っても過言ではありません。
ーーー
そしてこのタイミングでの掲載。
国道から奥へと緑が導くこの広場も、ねぶた祭りに限らず市民が集う場所。
建物が完成するまで 年、でもここから何倍もの時間使われていく新市庁舎。
これから市役所に求められるものも変化していきます。
職員の働き方も変容していくでしょう。
もしかしたら災害に見舞われることもあるかもしれません。
その変化を、そして変わらないことも、見ていきたいと思います。
ーーー
家が、店が、建物が、空間が誰かを支えている。
そんな仕事ができることを誇りに思って。
昨日から一転、冬に戻った青森で、今は現場に向かいます。
 建築模型づくり体験の参加申し込みは第一ホームまで!
建築模型づくり体験の参加申し込みは第一ホームまで!
八甲田山の冠雪のニュースの後、少し暖かい日が続いてちょっとホッとしている青森です。
暖冬の長期予報に少し期待をしつつ、霜月に突入。
気温は日々冬へと向かっています。
ーーー
さて、今年の春に八戸工業大学の准教授に着任してから早くも7ヶ月。
来る11月11日(土)に大学のサテライトキャンパス「ばんらぼ」にて体験公開講座を開催いたします!
3年生の設計課題は、株式会社第一ホーム所有の宅地を想定した八戸型コートハウス。
その最終公開審査が行われます。
実際に家づくりに関わりたい、と考える学生にとっては貴重な体験になるハズ。
大学を飛び出して街中でのプレゼンテーションも楽しみです。
ーーー
そして同日、体験公開講座の主役は子どもたち!
建築模型づくりを体験してもらいます!!
フクシアンドフクシは、以前から子どもたちの職業体験イベントに参加しています。
紙を折り、色をつけて、自分だけの家を作っていきます。
みんな夢中になってつくってくれる作品の何と魅力的なこと!
今回も未来の建築家に会えるのを楽しみにしています。
ーーー
建築を教えるハズが、この時ばかりは私たちもワクワクなのです。
ご来場は予約不要の無料です!
美術館やブックセンターなど八戸の街を歩きながら、どうぞお立ち寄りください!
 岩手山と北上川の景色は今日も変わらず出迎えてくれました
岩手山と北上川の景色は今日も変わらず出迎えてくれました
NYタイムズに「2023年に行くべき52か所」1位のロンドンに次いで2位に選ばれた盛岡市。
風もなく、街歩きには最適の秋晴れの日に訪れる機会がやってきました。
盛岡駅から程近く、存在感のある北上川が流れる川沿いの「木伏緑地」へ。
「water neighborhood~水辺界隈の生活者になろう~」をコンセプトに、飲食店やトイレが整備され、北上川に親しみ、キャンプも楽しめる、そんな場所。
いくつものコンテナがランダムに並び、デッキテラスやベンチもたくさん。
北上川の流れと緑あふれる景観に包まれて、訪れた人が思い思いの場所で、思い思いに楽しむ。
観光地特有のザワザワした感じもなく、場所のコンテンツが見事に活かされていました。
 多くの人がデッキでランチを楽しみ、川縁を散策する。(写真はあえて皆さん少ないカットで!)
多くの人がデッキでランチを楽しみ、川縁を散策する。(写真はあえて皆さん少ないカットで!)
ーーー
この「木伏緑地」、かつて舟で様々なものを運んでいた時代の拠点であったそう。
特に山から材木を運んできては、ここで下ろし、製材が盛んだったエリア。
川向かいは「材木町」という地名の通りその名残も。
歴史的な建物も多く残る盛岡市。
NYタイムズの記者が散策してその魅力に取り憑かれたのは頷けます。
ーーー
 材木町の通りには宮澤賢治にちなんだアート作品が並ぶ。今日はカボチャも一緒に。
材木町の通りには宮澤賢治にちなんだアート作品が並ぶ。今日はカボチャも一緒に。
続いてその材木町へ。
お気に入りは、もう何回も訪れている光源社さん。
町屋特有の細長い敷地を北上川へと抜ける外部空間が、毎回訪れるたびに感動をもらいます。
大きな紅葉が日差しを柔らかく遮って、何とも心地よい空間が待っていてくれました。
きっともう2、3週間もすれば色づいて、違った景色になるのでしょう。
次回はまた違った顔を見せてくれるに違いない、そう思わずにはいられませんでした。
 緑の屋根はもうじき赤に染まるのかも
緑の屋根はもうじき赤に染まるのかも
ーーー
 垂れ幕をかけて、車両通行止めで始まります!
垂れ幕をかけて、車両通行止めで始まります!
この日は夕方から毎週開かれている「よ市」の準備中。
暑く過ぎず、寒過ぎずのよき日に、多くの人が散策に繰り出していました。
人の噂に尋ねた場所が、何故だかまた行きたくなる。
「また来るね」そう声を呟いて帰途につきました。
そんな場所づくりをしていきたいと気持ち新たに。

気がつけば10月も半ばに差し掛かろうとしています。
あまりの猛暑、その長さに「これまでの常識」が覆された夏となりました。
コロナウィルスに全世界が覆われてから丸3年になろうとしています。
もうずっと大きな黒い雲に覆われていたようなこの3年。
終わりの見えない道を黙々と進んでいたようなこの3年。
10年くらいそうしていたような気がするこの3年。
でも明らかに再び世界は動き出しました。
いいことも、そうでないことも。
温暖化の影響が今年の夏の暑さだとしたら、来年以降も覚悟して備えなければなりません。
いいえ、夏の前に冬がやってきます。
どんな冬がやってくるのか、そのために必要な建築を考えなくてはなりません!
コロナ前に戻るのではなく、アフターコロナは新時代の到来といえるのでしょう。
ーーー
5月以降、想像以上にザワザワ様々なモノが動き出して何かと落ち着かない日々が続いていましたが
それでも現場サイドは着々と進行し、あるもの完成を、あるものは着工を迎えています。
間口5.5m足らず、奥行き24mの南北に細長い敷地に立つ住宅。
その長さを活かした土間と間仕切りのない空間。

その細長比はこれまでで最高。。。
ということは難しさも。。。
毎回異なる課題にチャレンジするのがこの仕事の醍醐味です!
もう少しで完成。
そのワクワク感をオーナーと共に味わえるのも、同様!
やっと来た澄んだ高い空に清々しい気持ちを味わっている今日この頃です。
ーーー
いつもなら、待ちに待った春に口をついて出る「さあ!」も、今年は思わずこの時期に出てきます。
遠くの山の「初冠雪」の頼りにドキッとしながら、今度は始まったばかりの現場に通います!

 古い柱と融合しながら新しいものを足していきます。
古い柱と融合しながら新しいものを足していきます。
線状降水帯発生のニュースが全国で飛び交っているこの1ヶ月。
以前は「梅雨がない」と言われていた青森も、降ったり止んだりの空模様が続いています。
つい先日は、日本海側には大雨警報も出され、一部被害も出てしまった文月です。
ーーー
新型コロナウイルス感染症は5月に「5類」としての扱いとなり、ここ数ヶ月でいろいろなことが一気に動き出した、と感じています。
春を待って着工することも多い北日本。
忙しさに拍車をかけている、そんな感じがします。
それに合わせ、最近の激しい気候。
現場の職人さんたちは本当に大変です。
ーーー
そんな中、南部町の改修工事が進行中です。
長年地域で親しまれてきた店舗の一部を改修して、お店を存続しながら、新たな居場所をつくっていくプロジェクト。
お店の奥には住まいが続き、質地は高台につながっていて、そこには大木が。
登ると周辺を見渡すことができる絶景。
なんて豊な景色なんだろう、と思わずにはいられません。
ーーー
人口減少による地方の過疎化は全国共通の課題、と言われています。
でもそこには唯一無二の価値もあります。
そしてそこに暮らしている人がいます。
それを見出し、その器となるデザインとは何か。
毎回異なる答えを探し続けています。
ーーー

今回は、既存のお店の中にすっぽり入る新しいハコをデザインしました。
これまでたくさんのお客さんに商品だけでなく居場所も提供してきたこの店が、これからも地域に生き続けるように。
ふらりとやってくる誰かのために、いつもどこかが開いている。
声を掛けると「ハーイ」と誰かが答えてくれる、そんな雰囲気を残しながら。
これから新しい人もやってきて、自然とそこに座っている場所になるようデザインしました。
 新築時、お祝いの鏡はそのままに。これからもここに集う人々を映し出します。
新築時、お祝いの鏡はそのままに。これからもここに集う人々を映し出します。
次の時代へと繋げるパーツのように、そっと、それでいてしっかりと根付くように。
白いキャンバスに、これからも自由にいろんな色が描かれていくように。
完全にリセットするのではなく、これまでの時間に重ねていけるように。
ーーー
完成はもうすぐ。
さくらんぼの季節が過ぎ、次は桃の季節でしょうか?そんな楽しみもある南部町への道を走ります。